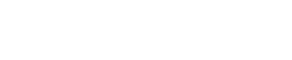本文
後期高齢者医療保険料のご案内
後期高齢者医療の被保険者になると、それまで加入していた国民健康保険、社会保険、共済保険等から脱退し、一人ひとりが後期高齢者医療の保険料を納めていただきます。
※加入した月から保険料がかかります。
保険料(年額)の計算方法
保険料 = 1.被保険者均等割額 + 2.所得割額(保険料限度額80万円)※1
1.均等割額・・・43,800円
加入者全員が人数割りで負担する額
※1 限度額の引き上げに伴う保険料の急増に配慮し、2年かけて段階的に引き上げ
(令和6年度に75歳に到達して被保険者となる方を除く)
令和6年度:73万円、令和7年度:80万円
世帯の所得に応じて軽減される場合があります。
〔軽減割合の所得基準〕
|
軽減割合 |
軽減判定所得基準(世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計) |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下の場合 |
| 5割軽減 | 43万円+(29.5万円×世帯内の被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者の数-1) 以下の場合 |
| 2割軽減 | 43万円+(54.5万円×世帯内の被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者の数-1) 以下の場合 |
2.所得割額・・・賦課のもととなる所得金額※2×9.11%(所得割率)※3
加入者の所得に応じて負担する額
※2 賦課のもととなる所得金額=総所得金額等〈前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短
期)譲渡所得金額等の合計〉-43万円(基礎控除)
※3 令和5年中の賦課のもととなる所得金額が58万円(公的年金収入211万円相当)以下の方は、令和6年
度の所得割率が8.45%となります。
保険料の計算例
被保険者一人世帯・年金収入220万円の場合
公的年金等に係る雑所得の金額 220万円ー110万円(公的年金等控除)=110万円
【均等割額】
均等割軽減判定:110万円ー15万円(特別控除)=95万円・・・2割軽減に該当
均 等 割 額:43,800円ー(43,800円×0.2)=35,040円
【所得割額】
所 得 割 額:110万円ー43万円(基礎控除)=67万円
67万円×9.11%=61,037円
| 均等割額 | 所得割額 | 合計 | 年間保険料額 |
|---|---|---|---|
| 35,040円 | 61,037円 | 96,077円 | 96,000円 |
夫婦ともに被保険者世帯の場合
夫の年金収入額220万円、妻の年金収入額210万円の場合
夫:公的年金等に係る雑所得の金額 220万円ー110万円(公的年金等控除)=110万円
妻:公的年金等に係る雑所得の金額 210万円ー110万円(公的年金等控除)=100万円
夫の保険料額
【均等割額】
均等割軽減判定:夫110万円ー15万円(特別控除)=95万円
妻100万円ー15万円(特別控除)=85万円
夫95万円+妻85万円=180万円・・・軽減該当なし
均 等 割 額:43,800円
【所得割額】
所 得 割 額:110万円ー43万円(基礎控除)=67万円
67万円×9.11%=61,037円
妻の保険料額
【均等割額】43,800円(夫と同額)
【所得割額】100万円ー43万円(基礎控除)=57万円
57万円×8.45%=48,165円
| 均等割額 | 所得割額 | 合計 | 年間保険料額 | |
|---|---|---|---|---|
| 夫 | 43,800円 | 61,037円 | 104,837円 | 104,800円 |
| 妻 | 43,800円 | 48,165円 | 91,965円 | 91,900円 |
保険料の納付方法・納期
原則として、年金からの天引きとなります。
| 納期 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 特別徴収開始通知書をご覧ください | 8月上旬にお知らせします | ||||
| 納期 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
※年金からの天引きとならない場合
- 年金年額が18万円未満の方
- 介護保険料を納付書や口座振替で納めている場合
- 介護保険料+後期高齢者医療保険料の合計金額が、年金額の2分の1より多い場合
コンビニエンスストア・スマートフォン決済での納付が可能となりました。
※ただし、納期限が過ぎた納付書、破損や汚れによりバーコードを読み取れない納付書、1枚あたりの金額が30万円を超える納付書は、コンビニエンスストア・スマートフォン決済では使用することができません。(金融機関では使用できます。)
被用者保険の被扶養者であった方への軽減措置
後期高齢者医療制度加入時に被用者保険の被扶養者であった方は均等割額の5割が軽減されます。(加入した月から2年間)
※所得に応じた均等割額の軽減に該当する場合は、軽減割合の高いほうが優先されます。
保険料の変更について
次のような場合、後期高齢者医療保険料が後日変更になる場合があります。
- 税金の申告が遅れたり内容変更があった場合
- 減免があった場合
- 転入してきた場合
- 資格喪失(死亡や転出等)があった場合