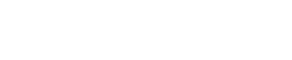本文
村の事件簿1 継送りされた病人
継送りされた病人
富永家文書は、江戸時代、旗本竜島酒井家の領地だった下佐久間村(鋸南町)の名主、富永家に残された膨大な村方文書で、その数約三〇〇〇点にも及びます。現在は資料館に保管され、解読作業が進められてきましたが、内容を読み解くにつれ、当時の村の様子やしくみ、さまざまな事件がよくわかる貴重な資料です。その中から、下佐久間村で起こったある事件を紹介します。
天保二年(一八三一)八月、五井宿(市原市五井)の名主から内房の街道の継立(つぎたて)の村々へ回状が廻りました。ある病人を市部村(南房総市市部)へ継送りするのでよろしくお願いするという内容です。その病人とは市部村の百姓八兵衛の倅で久七と言います。
久七は、漁船乗りをしていましたが、江戸の魚問屋へ魚を卸した帰り、仲間はすぐ帰りましたが、久七だけは用事があると残りました。しばらくして江戸を発ち帰路につきましたが、途中で病気になり、薬を買い服用しながら向かいますが、手持ちの路銀も無くなり、路頭に迷いながら八月十七日、五井宿までたどり着きます。名主儀兵衛は、日も暮れたので久七を家に泊めてあげます。その夜、にわかに病状が悪化し苦しみだす久七。医者を呼び見せたところ、難病にかかっているとわかり、しばらく療養させ、三日後にようやく快方に向かいだしたようです。
儀兵衛は、久七に、二三日休んだら歩いて国元へ帰るように言い聞かせましたが、久七はどうしても国元へ送り届けてほしいと、あまりにも願うので、しかたなく本人の願いを入れて、行く先々の村々にこれから病人が市部村まで向かうので、受け入れ準備等をお願いしたい旨の回状を送ったのです。この回状が市部村に着く頃には、戸板に乗せられた久七が街道を南下してきているはずです。
八月二十七日、久七が下佐久間村へ送られてきました。すぐに市部村へ送り届けたところ、市部村の名主惣兵衛は、なんと久七の受け取りを拒否したのです。惣兵衛の言い分は、その者は不埒者ゆえ、先年、帳外にした、つまり村を追放した者だから受け取れないと言うのです。しかたなく下佐久間村の人足は再び担いで戻ってきました。
自分から帰りたくないとグズグズしていたのも道理。実は久七、帳外者だったのです。
江戸時代の戸籍にあたるのが人別帳です。各村では家ごとに名前、続柄、年齢、宗派を記した帳面を作成し、管理していました。さて、いつの時代でも不良や迷惑者はいるもので、もし何か悪さをしでかせば一家、近所の五人組で連帯責任を取らされます。そのため、どうしても改心しない者は、最終手段として勘当して縁を切り、人別帳から除外します。これを「久離帳外」(きゅうりちょうがい)と言います。つまり村には居られなくなり無宿者となるのです。またそうなる前にも、こいつは何かしでかしそうな悪だという者は、人別帳にあらかじめ付箋を貼っておいて、要注意人物がわかるようにしておきます。よく「あいつは札つきの悪だ」と言いますが、これは人別帳に付箋の札が貼ってある人間だという意味が語源なのです。
久七は帳外になったので、故郷には帰れなかった。病気になったのを幸いに、村の継送りで帰されれば、病人だし、市部村も受け入れてくれるだろうと考えたのでしょう。ところが考えは甘かったようです。
さて困ったのは下佐久間村の名主、富永繁太郎。地域の大名主である勝山村に仲介、説得を頼みますが、らちが開きません。やむを得ず、下佐久間村は久七を手前の竜島村へと送り返しました。
さあ、こうなったら雪崩(なだれ)式です。送り返された村は、その前の村、前の村と送り返して、久七は湊村(富津市湊)まで戻ってしまいました。
これに、まったをかけたのが湊村の名主、角兵衛です。市部村、勝山村両村に対し、この理不尽な仕打ちを批判した書状を付けて、再び送り返してきました。久七、またも街道を往復します。
「市部村は始末書も付けずに送り返すのはどういうことだ。継送りの村で多額の人足費用を無駄にしていることに気遣いもない。帳外者であっても、勝山藩領の御陣屋もあることだし、大名主の勝山村は役所へ相談して引き取り、他村へ迷惑のかからないようにすることが筋だろう」と。
まさに正論の角兵衛の意見に、勝山村は急遽陣屋に掛け合い、市部村は久七を受け取り、介抱することになりました。増え続ける帳外者の対処と名主の責任能力が問われた事件でした。
 「房陽郡郷考」(内房の村々が記されています)
「房陽郡郷考」(内房の村々が記されています)