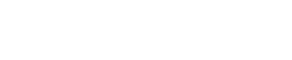本文
水戸黄門がやって来た
水戸黄門がやって来た
光圀、水戸出発
水戸黄門とは徳川御三家の水戸藩二代藩主、徳川中納言光圀です。徳川家康の孫にあたります。中納言のことを唐名で黄門と言うため、水戸黄門と呼ばれました。のちに「水戸黄門漫遊記」などの講談や読み本、また映画やテレビ時代劇などで、諸国を旅して悪人を成敗するその脚色されたストーリーが人気となり、誰もが知る人物となります。
しかし実際の光圀は、あのように諸国を巡ったわけではありませんし、悪人退治に首を突っ込むことはありませんでした。とは言え、エピソードの多い人物ではあります。晩年は水戸の西山荘に隠居し、庶民とも親しく接し、また学問を推奨し、「大日本史」という歴史書の編纂を行なっています。これは水戸藩の事業として、光圀の死後も続けられた一大プロジェクトとなります。
聖人君子の鑑と思われている光圀ですが、実は若い頃は、かなり過激な若様だったようで、江戸の町では市中の悪仲間と不良のような行状を繰り返していたと言うから驚きです。
さて、その光圀、勝山(鋸南町)を訪れているのです。父頼房の養母にあたる英勝院お梶の方の墓参のため鎌倉の英勝寺への旅。水戸から房総を南下し、湊村(富津市)から船で対岸金澤に渡り鎌倉へ向かうルートでした。実は光圀としては「大日本史」編纂の調査を兼ね、地方史料の収集や史蹟の見分なども目的だったようです。延宝二年(一六七四)、光圀四十七歳、まだ隠居する前の水戸藩主の時です。
この時光圀が記した紀行文「甲寅紀行」から、光圀の旅の行程をたどってみましょう。
四月二十二日、水戸を出発、その夜は小川村泊。二十三日は板久(潮来)の旅館泊。二十四日は雨で滞留。翌二十五日にここまで送って来た近侍五、六人を水戸へ帰しています。その夜は押砂(稲敷市)の祥雲寺に泊りました。こう見ると、徳川御三家の殿様の旅とは思えない、一般の旅籠や寺に泊まるような少人数のお忍びの旅だったことがわかります。
二十六日は押砂から利根川を船でさかのぼり、神崎の神崎神社を参拝し、成田を通り、成田不動尊に参詣、酒々井村の地蔵院に泊。二十七日は千葉に向かい、千葉寺を調査。蘇我、浜野、八幡、五井を過ぎて姉ヶ崎村の妙経寺に泊。二十八日は椎津、久保田、中島、奈良輪を経て木更津に着き、小休止し昼食をとっています。
光圀、浮島に感激
延宝二年(一六七四)四月二十八日、姉ヶ崎を出た徳川光圀は、木更津で昼食後、君津から相野谷の房総往還を通り、佐貫村を経て湊村(富津市湊)に着きました。この時は佐貫城主の松平重治の用意した旅館に泊まっています。
翌二十九日、午前八時頃、旅館を出発した光圀は、湊川を渡り、対岸の十宮から船に乗り、安房へ向かいました。鎌倉へ向かうには、少々寄り道となります。勝山藩には知らせは届いていたのでしょう。光圀の船が鋸山妙鐘崎を廻ると、勝山藩からの出迎えの船が十四、五艘飾り立てて待っていたそうです。この時の勝山藩主は初代の酒井忠国(初名は忠栄)。徳川御三家水戸藩の藩主がお忍びとは言え、自分の領国に来るのです。さぞ気を使ったことでしょう。
光圀はまず船で浮島を一覧してから勝山に上陸しました。光圀は「甲寅紀行」にこの時の様子をくわしく記しています。わかりやすく紹介すると、
「勝山の前十町ばかり沖合いに浮島という島がある(一町は一〇九メートル)。岩石がごつごつしてとても奇抜で優れた景色だ。大きな洞穴が二つ。その穴は向こうへ通り抜けている。南方に少し離れて、一段と美しい岩がある。伽羅(香木)を割ったような形だ。浮島の大きさは南北三町ほど、東西一町ほど。島の上には一面小笹が生い茂り、ところどころに小松もある。浮島大明神という社があるらしい。勝山の浜辺の岩の上に小さな鳥居がある。また浜辺に離れて小島がある。ミサゴ島とも傾城島とも言うらしい。勝山村で昼食をとり、崖にあがりこのあたりを見めぐった。」
光圀は浮島の景観にいたく感激したようです。当時、浮島本島と大ボッケ島はつながっていたと思われます。その間に穴があったので、現在確認できる大ボッケの穴と合わせて二つの穴があったという光圀の証言となるのでしょう。元禄の大地震で二島の間は崩れたと伝わります。伽羅を割ったような岩とは小ボッケのことでしょう。
さて光圀は勝山に上陸し昼食をとります。光圀が昼食休憩をとったのはどこなのか。勝山藩邸で接待を受けたと思いきや、どうやら海際の大黒山ふもとあたりの、ある浪人の家に立ち寄って休息することになったようです。光圀らしいと言えば、らしいですが。その浪人の名は石井弥五兵衛収と言います。この後、水戸藩に仕え、「大日本史」編纂の有能なブレーンとして光圀を支えることになる人物です。
光圀、人材を得る
延宝二年(一六七四)、勝山にやって来た水戸黄門こと徳川光圀と出会った石井弥五兵衛収(いわいやごべえおさむ)とは、どんな人物なのでしょうか。彼は山荻村(館山市山荻)の生まれで、家系は安房里見氏の一族から出ています。祖父盛次は里見家改易後、入国してきた徳川代官のもとで手腕を発揮しています。
弥五兵衛は幼い頃より書をよくし、詩文も得意で、三朶花(さんだか)と号しました。やがて本多出雲守政利に仕えましたが、すぐに辞して安房に帰り、勝山に住んでいたようです。浪人となった弥五兵衛は、勝山大黒山あたりに家を構え、畑作業や釣りで妻子を養っていたと言います。
光圀はひょんなことから弥五兵衛の家で昼食をとることになりました。いえ、ひょっとしたら、光圀は弥五兵衛という人材を聞き知って、面接のような気持ちがあったのかもしれません。「大日本史」という日本の歴史を忠実に著そうと決意した光圀にとって、各地の歴史や史料に精通し、文才のある人材は、これからいくらでもほしかったはずだからです。弥五兵衛は、この年の十二月から江戸小石川の水戸藩邸に右筆として仕えることになりました。二十六歳のことです。
やがて「大日本史」の編纂にたずさわるようになり、他に詩文集の編纂も任され、光圀の信任をさらに厚くしました。光圀の命で安房の史蹟調査、史料収集に出張したこともありました。この時、里見氏菩提寺の延命寺(南房総市本織)で里見系図二巻を発見して、これを写し取り、「大日本史」の諸家系図資料に掲載したのは弥五兵衛の功績です。
水戸藩の彰考館に出仕し編纂事業に尽力した有能な人材たちは、石井弥五兵衛に限らず、日本各地を現地調査し、その史料の発掘を重視しました。彰考館総裁だった佐々介三郎宗淳、安積覚兵衛澹泊などはその中の代表格です。これが、水戸黄門自身が日本各地を漫遊したという物語に脚色されて世に広まります。そしてこの佐々介三郎が助さん、安積覚兵衛が格さんとして、黄門様のお供に脚色されたのです。
弥五兵衛と介三郎は同じ年に召抱えられ、彰考館でも肩を並べていました。もし「水戸黄門漫遊記」の作者が、石井弥五兵衛のことを、もう少し知っていたなら、黄門様のお供は、助さん格さんではなく、助さん弥五さんになっていたかも知れませんね。
光圀、鋸山難所越え
さて勝山で休息した徳川光圀は、ここから反転して帰路につきます。今度は馬に乗り、陸路、保田方面へ北上。勝山の出はずれにあった日月の宮、現在の加知山神社前を通って、竜島へ向かいます。
竜島から大六、吉浜と通る光圀。妙本寺に目をとめ、五十石の御朱印寺と記しています。この道のりで、どうやら道案内が付いていたと思われ、光圀は馬の背に揺られながら、目にする地形や寺社を質問したのか、細かく「甲寅紀行抄」に記しています。
「大帷子村と吉浜との間に保田の権現山というあり、その奥には志賀峰という山あり、富士山という丘山もあり、保田村に至る、川上を小保田という、海の方に八幡山というあり、その内に八幡の社あり、本名村に岩戸観音あり、その山上に大福山日本寺とて薬師あり」
そして、いよいよ鋸山の突端、岩場伝いの妙金の難所を越えることになります。まず商人橋という小さな架け橋を渡り、岬の小道を岸に沿って行きます。左はすぐ海です。桶嶋、白ごね嶋、烏帽子石、布引石、茶坊主石、さらに頼朝伝説にちなんだ冑島、鞍掛け石といった岩も見えると光圀は記しています。
明金崎を過ぎたあたりは日蔭が浦と言い、少し奥まった所は屏風蔵という狭い谷合です。
「日蔭が浦に、昔通りし人の藤縄をさげたる穴の跡あり、ぢょん切り山とて、切り立ちたる如くなる山、道の右にあり」「明金の内に八町ばかり難所あり、荷付馬通る事ならざる間、一町半余あり」(一町は一〇九メートル)
昔は岸壁に藤縄をたらして、それを伝って通ったのでしょうか。光圀の通った時は、それより少しは整備されていたとは言え、かなりの難所でスリリングなところだった事が目に浮かぶような光圀の書き方です。
ともあれ、聞きしに勝る明金の難所を越えた光圀は、湊村に戻り旅館で二泊、そこから船で対岸の金澤に渡り、鎌倉へ入りました。英勝寺を墓参し、鎌倉の名所旧跡を探訪した後、五月九日、江戸小石川の水戸藩邸に戻りました。
石井弥五兵衛は享保九年(一七二四)七十六歳で水戸で亡くなりました。墓は、水戸偕楽園近くの神崎寺にあります。

参考 「安房先賢偉人傳」 大野太平編集 昭和13年