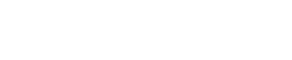本文
勝山藩の戊辰戦争
勝山藩の戊辰戦争 ー幕末房総のラストサムライー
旧幕府軍の江戸脱走
薩長を中心とする官軍に江戸幕府方が最後の抵抗を見せたのが、鳥羽伏見の戦いに始まる戊辰戦争です。幕臣としての意地から、時代の大きなうねりの中であらがい、多くの者が命を落としていきました。その悲劇は勝山藩にも起こっています。
慶応4年(1868)4月、勝海舟の尽力により官軍に江戸城が明け渡されると、それを不服とする旧幕府軍のいくつかの諸隊は、再起を図って江戸を脱走します。新撰組の近藤勇は下総流山に、歩兵隊の大鳥圭介は市川に、撒兵隊の福田八郎右衛門は木更津に集結しました。彼らはその後、会津、箱館と転戦していくことになります。木更津の撒兵隊は近隣の村に分営して義軍と称し、農民から食糧や金を略奪し、気勢を挙げていました。
請西藩主、林忠崇の義挙
木更津に請西藩(じょうざいはん)という一万石の小藩がありました。藩主の林昌之助忠崇(ただたか)は、この時21歳の青年藩主です。小藩とは言え、林家は徳川家とは因縁浅からぬ間がらで、家康の祖先がまだ松平と名乗り、三河に家を起こす前のこと。僧として諸国を回っていた松平親氏が、信州林郷の林家の祖先、林光政の館に宿泊した時、光政は一匹のウサギを捕え、元日の吸い物にしてもてなしました。後に松平家に仕え旗本となった林家は、毎年正月の吸い物用に、将軍家にウサギを献上するのを例とし、諸侯に先んじて一番に盃を賜り、これを「献兎賜盃」(けんとしはい)と言い、誇りとしてきました。家紋には一番盃を意味する一の文字を入れていたため「一文字大名」とも呼ばれていました。
林忠崇は、若年ながら気骨があり正義感が強く、まさに一本気な性格でした。撒兵隊の福田は、忠崇に決起をうながしますが、規律に乏しい撒兵隊に、忠崇は同調しきれずにいました。
その頃、榎本武揚率いる幕府艦隊に乗船し木更津に上陸したもう一つの脱走隊がありました。伊庭八郎、人見勝太郎に率いられた幕府遊撃隊です。伊庭と人見に面会した忠崇は、剛柔兼ね備えた真摯な両名の性格に、即座に協力を約束しました。この三名の出会いにより、勝山藩を含む内房諸藩は、いやがおうにも動乱に巻き込まれていくことになるのです。
慶応4年閏4月3日、藩主自ら脱藩という前代未聞の挙に出た忠崇は、従う藩兵約70名、遊撃隊士36名で挙兵。義軍と称し、号砲一発、真武根陣屋(木更津市真船)を進発し、内房を南下してきました。出陣に際し、忠崇は陣屋を焼き払いました。もはや帰ることのない決意の表れです。忠崇の作戦は、内房諸藩と連携し援軍を募り、海を渡って伊豆に入り、小田原藩と同盟して、箱根を押さえて官軍を迎え撃つというものでした。
伊庭八郎と人見勝太郎
請西藩と遊撃隊で組織された義軍の挙兵により、内房諸藩に緊張が走りました。遊撃隊とは、腕の立つ旗本御家人の子弟で編成された、言わば将軍親衛隊です。隊長は伊波八郎。心形刀流の伊庭道場、伊庭軍兵衛の長男として江戸に生まれ、文武に優れ、幕府講武所剣術師範となり、徳川慶喜を護衛して上方へ上り、鳥羽伏見の戦いに敗れて江戸へ戻ってきました。白面の美男子で、その剣技は「伊庭の麒麟児」と称賛されたほどの使い手。この時25歳でした。
一方、人見勝太郎は、京都二条城の鉄砲奉行組同心、人見勝之丞の長男として生まれ、京都文武場の教授であった父の影響で学問、剣術に優れた才能を発揮、京都所司代与力となりました。遊撃隊に加わり、八郎とともに江戸へ敗走後、遊撃隊の一部を率いて江戸を脱走しました。この時26歳です。
内房諸藩の苦慮の決断
請西藩主、林忠崇を盟主とする義軍は、まず富津砲台を守備する富津陣屋(富津市)に迫りました。警護の前橋藩は、老臣小河原多宮が、歩兵23人を脱走したことにして援軍として送り、他に大砲六門、小銃十挺、金五百両を差し出しました。小河原はその夜、責任を取って切腹しています。
ついで飯野藩では、藩主保科正益は上洛中であり、老臣樋口弥一郎は、やむなく兵20人を差し出しました。佐貫藩では、藩主阿部正恒は金三百両と兵器を送り、援兵は体よく断っています。
そして閏4月7日、保田芝台(鋸南町)付近に宿陣した林軍は、いよいよ勝山藩に援兵を迫りました。この時、藩主酒井忠美はわずか6歳。江戸にいて不在です。家老の酒井勇雄は蝦夷地へ出張中。留守居の岡田文左衛門らは苦しい選択に迫られました。
この頃、諸藩は勤王証書というものを提出させられ、官軍に忠誠を誓わされていましたが、意気上がる林軍に抵抗すれば、領内を戦火に巻き込むことになります。勝山藩でも、やむをえず福井小左衛門ら31名を半ば脱藩の形で援兵として差し出したのです。彼ら勝山藩士の名は次の通りです。
福井小左衛門、楯石作之丞、高橋万吉郎、智作太郎、須藤静摩、加藤六郎、小暮波五郎、竹内利兵衛、高橋種助、渋谷兼吉、秋子松五郎、川名儀兵衛、佐久間徳蔵、高橋徳太郎、須藤弥八郎、渡辺半蔵、小林栄吉、大沢和四郎、矢島四郎兵衛、戸塚辰五郎、山東林蔵、安田定七、滝本岩吉、松坂佐左衛門、山口(柴田)多郎三郎、松坂啓造、忍足徳蔵、福井小左衛門の従者として山根房吉、平四郎、義兵衛、岩井伝三郎の31名です。
館山から伊豆へ
続いて林軍は、長須賀村(館山市)に着陣。館山藩では、藩主稲葉正善は不在でしたが、前藩主の正巳がいました。稲葉正巳は、わずか二ヶ月前まで老中格として海軍総裁を兼ね、幕府陸海軍の洋式化に力を注ぎ、敏腕をふるった人物で、「洋人殿様」とあだ名されるほど外国通の名君でした。
正巳の態度を計りかねた林軍は、武装して陣屋を取り囲みます。館山湾からは自ら手塩にかけた榎本武揚率いる艦隊から威嚇砲撃もされました。結局館山藩からは14名の援兵を差し出させました。
内房諸藩の援軍を得た林軍は、館山から海路伊豆へ向けて出発しますが、その出発の朝、諏訪数馬という請西藩士が切腹しました。彼は労咳をわずらって寝たきりでしたが、藩主忠崇にどうしてもと願い出て、ここまで従軍してきました。しかし足手まといになることを憂い、ついに自ら命を絶ったのです。この時、忠崇自ら介錯をしました。これからの林軍の運命を暗示させるような悲痛な出来事でした。
敵か味方か小田原藩
館山柏崎から和船二艘に乗り込み、真鶴崎(神奈川県真鶴町)に上陸した林軍は、小田原藩との交渉に入りました。忠崇自ら小田原城に出向きましたが、藩主大久保忠礼は会おうとはせず、武器や兵糧は差し出すが、自重するようにと言われます。小田原藩は箱根を押さえる要として、官軍側でもかなり厳しい監視の目を光らせており、藩内では官軍側、佐幕派と揺れ動き、はっきりしません。しかし、相模湾に停泊する榎本艦隊の無言の圧力により藩内は佐幕に傾きました。
林軍は、その後伊豆の各地を転々とし、沼津に宿陣しています。駿府勤番の脱藩兵などを加え総勢275名に達していた林軍は、小隊編成され、勝山藩士は福井小左衛門を隊長とし、第一軍の一番小隊となりました。つまりこれは戦いの最前線に立つということです。これが勝山藩の悲劇となります。
5月19日、上野の彰義隊開戦を聞いて、連携すべく東へ向かった林軍は、小田原藩が守る箱根の関所へ到達しました。佐幕に決していた小田原藩は、官軍の軍監(監視役)を追放。林軍は関所を占拠します。これを知った江戸の東征大総督府は、ただちに小田原藩の江戸藩邸を没収、小田原藩に問罪使と長州藩ら四藩の大軍を派遣しました。これにより小田原藩は再び官軍に寝返ることになります。
箱根湯本に山崎という地名があります。小田原方面から箱根への上り口の入り口にあたる場所で、ここに林軍の第一軍と第二軍が布陣。林忠崇の本陣は芦ノ湖畔です。対するは、官軍の大軍に後から監視され、引くに引かれぬ小田原藩。5月26日、ついに箱根山崎の戦いが幕を開けます。
箱根山崎の戦い
官軍に追い立てられて、昨日の盟友を討つ小田原藩は、士気が上がらず苦戦を強いられます。見かねた山上の官軍が砲撃で参戦し、形勢は逆転しました。三枚橋付近が激戦地となりましたが、小田原藩兵千、官軍四藩二千に対し、山崎に布陣した林軍はわずか百二十。勝敗のゆくえは火を見るより明らかでした。
夕刻、林軍は次々に敗走。闇夜の箱根山中をさまよい、敵兵に掃討されました。多くの負傷者を出して、箱根の関所に引き揚げてきたのが午後7時頃。どの顔も皆どす黒い血と土埃にまみれ、無残な姿でした。この戦いで特に壊滅的な打撃を受けたのは、最前線に立った勝山藩士です。31人中、戦死15、戦傷10、行方不明2というほぼ全滅の状態でした。
三枚橋にほど近い早雲寺に勝山藩士としてただ一人、竹内利平が葬られています。おそらく早い段階で戦死したため、この寺に運ばれたのでしょう。彼は勝山藩領だった群馬の下高浜村の生まれで、この時20歳でした。その他の藩士たちは元箱根の本還寺に葬られたと言います。
その戦死者の中の一人、須藤静摩は、勝山藩分限帳によると殿様の身の回りの雑用をする御側坊主で、この時23歳。加増されて髪を伸ばすことを許されていました。その他は分限帳に名が記されていません。藩領から集められた農兵だったのか、あるいは後に意図的に分限帳から名が消されたのかもしれません。
敗残帰藩
一方、第二軍を指揮した伊庭八郎は、敗走の途中、敵の玉を受け、小田原藩士、高橋藤太郎に左腕を切られました。右腕で敵を倒した八郎は、気丈にも近くの民家で焼酎をもらい、傷口を洗い包帯をして引き揚げたと言います。しかし、左腕は切断されることになり、以後、片腕の剣士として箱館戦争まで戦い抜くことになります。
林軍は再起を図るべく、熱海への間道を通って、網代から船で再び館山へと敗走、ここで負傷者らを下ろし、奥州へ向かいました。生き残った勝山藩士らを含め、内房諸藩の脱藩兵らは、ここで各藩へ帰っていきました。
勝山藩士で帰ってきた者は、福井小左衛門、楯石作之丞、大沢和四郎、矢島四郎兵衛、小林栄吉、山東林蔵、山口多郎三郎、松坂啓造、忍足徳蔵、山根房吉、平四郎、儀兵衛、伝三郎のようです。彼らはひとまず勝山の内宿の薬師堂に集められました。
林軍に加担した兵が戻ってきたことは、やがて官軍に知られることになり、関係諸藩は厳しく調べられます。もちろん諸藩に弁解の余地はありません。官軍の駐屯する佐貫(富津市)の三宝寺へ責任者の出頭が命じられました。
義に殉じた藩士たち
慶応4年6月12日、佐貫の三宝寺において、林軍に加担した内房諸藩の責任者は切腹しました。富津陣屋の前橋藩では、老臣白井宣左衛門が切腹、飯野藩では樋口弥一郎と脱走兵の帰還者、野間銀二郎。野間は士分でなかったため打ち首でした。
勝山藩では、福井小左衛門と楯石作之丞が切腹。介錯は勝山藩士平井名実衛でした。彼は勝山村大名主でもあり、慶応3年に高二十三石で中小姓格となり、後に明治になって国宝と名乗り、戸長として村を導いた有能な指導者です。この時は28歳。豪放磊落な性格で剣をよくした彼は、命じられたとは言え、どのような思いでかつての同僚の首を打ったのでしょうか。
福井小左衛門。名は義靖。馬廻本格大目付五十石。上級藩士の一人で、この時27歳。独身でした。藩が提出した勤王証書に代表として署名していた彼ですが、時代に翻弄された彼の人生は察するに余りあります。
楯石作之丞。名は粛。吟味役六石。後に指令司。いわば下級将校です。この時35歳。志うという4歳になる娘が一人いました。二人の墓は三宝寺にあり、勝山藩は永代供養料として金五円づつを供えました。
義士の碑建立
それから23年後、明治23年(1890)6月12日、彼らを讃える碑が建てられました。発起人は勝山藩ゆかりの人たちです。
元勝山藩留守居役で、後に勝山戸長を勤めた岡田文左衛門貞寿。貞寿の娘婿で勝山藩剣術指南役だった服部利器。前述の平井国宝。元勝山藩士で竜島小学校教員、後に勝山村初代助役の宗村正興。元勝山藩士で安房郡書記となった大谷清海。勝山藩文学教師の野呂道庵の子息、野呂英臣。道庵の高弟で、郡会議員、県議会議員を勤めた早川儀之助らです。
碑の撰文は、漢詩文を得意とした早川儀之助です。碑文によると、当時、官軍から藩に責任追及が及んだ時、苦渋の老臣たちを前に、福井、楯石両名が静かに口を開き、「私たちが皆に代わって謝罪いたします。どうか心配なさらないで下さい」と、進んで官軍の幕営に出向き、切腹したとあります。
碑文上部の篆額(題字)には「視死如帰」と刻まれています。勝山藩士が属した第一軍の指揮者、人見勝太郎の書です。その意味は、死することはまるで家に帰るようなもの。恐れずに受け入れる、という意味です。自己を犠牲にして、藩と領民を戦火から救った彼らの行為は、勝山の人々の胸に深く刻まれました。この碑は、妙典寺に建てられています。
箱館で戦った勝山藩士
さて戊辰戦争は、その後、東北、箱館へと舞台を移し、明治2年(1869)5月18日、箱館五稜郭の開城をもって終結しました。この箱館戦争に参加し、戦死した一人の勝山藩士がいます。彼の名は三宅熊五郎。林軍に身を投じた藩士たちの中には見えない名です。彼がなぜ、どのような経緯で箱館に渡ったのか、今となっては知るよしもありません。ただ箱館の実行寺(函館市船見町)にある箱館戦争犠牲者の墓の中に、明治元年12月17日に戦死した彼の墓があります。
三者三様の人生
さて、内房諸藩を巻き込んだ義軍の中心人物、林忠崇、伊庭八郎、人見勝太郎の三人は、その後どうなったのでしょうか。
伊庭八郎は、左腕治療のため、林、人見に遅れて、奥州行きの榎本艦隊の美加保丸に乗船しましたが、不運にも暴風雨で美加保だけが銚子沖で沈没、かろうじて脱出した彼は、江戸、横浜と潜伏した後、箱館に渡りました。箱館政府のもと、歩兵頭並に任命された八郎は、片腕ながら松前で遊撃隊を率いて奮戦しましたが、明治2年4月20日、木口内で胸に銃弾を受け箱館病院へ収容されました。
そして官軍の五稜郭攻撃が始まる中、5月12日、病床でモルヒネを飲んで自殺したと言われます。彼は最後まで幕臣としての意地と誇りを見せて逝きました。
人見勝太郎は、奥州から箱館へと転戦し、箱館政府では松前奉行に任命され、遅れてきた伊庭八郎とともに松前、江差を守備しましたが、戦線で負傷し、箱館病院に収容中、五稜郭開城とともに降伏しました。その後は明治政府に仕え、茨城県令を勤めたり、利根運河会社を設立し実業家としても成功しています。また彼は、箱根早雲寺の遊撃隊士の墓碑を建立したり、勝山藩義士の碑の篆額を請け負ったりもしています。人見は明治政府のもとで生きる決断をしたのです。
林忠崇は、奥羽越列藩同盟の東北諸藩とともに奥州各地を転戦しましたが、盟主の仙台藩が降伏し、徳川家の存続が決まったこともあり、仙台藩の勧めで明治元年9月20日に降伏しました。徹底抗戦を主張する人見ら遊撃隊と別れて、忠崇主従19名は東京に護送されました。戊辰戦争を通じて唯一廃藩となったのは請西藩だけです。忠崇はこの時死を覚悟し、辞世の句を詠んでいます。
「真心のあるかなきかはほふりだす 腹の血潮の色にこそ知れ」
唐津藩屋敷に預けられた忠崇は、明治5年に禁を解かれ請西に帰農、その後は職を転々とし、赤貧ながら一夢と号し、和歌を愛する風流な人生を過ごしました。明治30年には鹿野山(君津市)の義軍の招魂碑の建立に携わっています。
昭和16年(1941)1月22日、忠崇は94歳という天寿をまっとうしました。臨終に際し辞世を求められると、彼はこう言ったそうです。
「明治元年にやった。今はない」
徳川のためただ一人、藩主の座を投げうって立ち上がった大名は、皮肉にも戊辰戦争時に存在した三百諸侯の中で、誰より長生きし、文字通り最後の殿様となったのです。