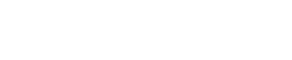本文
日入間が崎
日入間ケ崎(「鋸南町史」(昭和44年刊)より)
下佐久間の名主富永家所蔵の地図に次ぎのごとく書き込まれていた。天保7申年9月写之 田町三左衛門
「里人語り伝えて云う。ひいるまが崎とは昔、何の入道とかや申せし人(俊成入道と申伝れども不詳由)いかなる罪にや有けん、都より此処に左遷ましませし時、船を磯に着けて則上陸をすすめけるに、彼の人涙せきあへず、遥に西の空をうち詠めて、一首の歌をつらねられける。
『ふるさとは日の入るかたと詠むればかわかぬ抽に八重の志ほかぜ』
かく詠ぜられけるを、もののふども哀とも息はで、ひたすらに道急ぎしたりければ、
『情を知らぬ振舞哉この世の鬼とはこれなるべし』
と申されしより、舟の着きたる所をば、鬼ケ崎とは申し伝へり。
そのかたわらなる小島をは″彳島″と名づくるは、立ち止まりて、ふるさとをかへりみられし所也。″入道蔵″と申すは此岬に仮居せられし所といふ。即半年堂といへる古跡ありて、近きころまで、居室のあとと申し伝へしが、今は風雨に崩れ、波に破れて、名のみ残れる斗なり.その処より、仏具の金物或やき物の類掘出せし事杯、稀々ありしとかや。
このあたりを日いる間が崎と申し伝ふも、かの歌によるゆゑなりとぞ。
かの入道殿はこの処に半年が間ましましけるが、ほどなく帰洛せられけるよし、奉り伝へはべりぬ」
後、蛭間、或は、ひるまさ(昼正)という。かつて勝山、下佐久間が一村であった頃の名残りか、この付近の陸地畑は下佐久間村の飛地となっており、海面は、初めは下佐久間村で漁業をしたが、後勝山村の支配海面となった。しかし元禄の頃から岩井袋村から入会を主張し、一時は収まったが、寛政7年小網かけの問題を端緒として、同11年勘定奉行所の結審に至るまで、加知山、岩井袋、下佐久間3か村を巡る大紛争を巻き起したいわく付きの場所である。なお宝永年間には、村境を巡って岩井袋下佐久間村の争となり、7年に結審となった。
最近この付近を埋立て、宅地を造成し観光施設を設け、南房理想郷と名づけている。