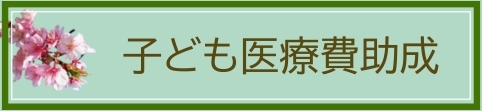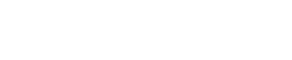本文
未熟児養育医療費の給付
身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児に対して、その治療に必要な医療費を公費で一部負担する制度です。(県内外問わず)指定養育医療機関での治療に限られます。
【参考】千葉県内の養育医療指定医療機関
所得に応じた自己負担金が生じますが「子ども医療費助成制度」等の対象となるため、これを充当させることができます。
※申請の際に、窓口でご意向をうかがいます。
対象者
鋸南町に住民登録があり、養育医療の対象となる未熟児であると認められること。
下記の1または2のいずれかの症状を有し、医師が入院養育を必要と認めた乳児。
※出生時から一度も退院していないケースに限ります。
養育医療の対象となる未熟児
身体の発育が未熟のまま出生した乳児であって、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのものをいいます。
たとえば、出生直後に次のいずれかの症状が認められるお子さんをいいます。
1.出生時体重2,000グラム以下であること
2.生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示していること
(1) 一般状態
ア 運動不安、痙攣があるもの。
イ 運動が異常に少ないもの。
(2) 体温が摂氏34度以下のもの。
(3) 呼吸器、循環器系
ア 強度のチアノーゼが持続するもの。チアノーゼ発作を繰り返すもの。
イ 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、毎分30以下のもの。
ウ 出血傾向の強いもの。
(4) 消化器系
ア 生後24時間以上排便のないもの。
イ 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの。
ウ 血性吐物、血性便のあるもの。
(5) 黄疸
ア 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの。
イ 交換輸血が必要な重症黄疸児。
(6) 前記(1)~(5)に準じる症状を有しており、特に入院養育が必要なもの。
※主治医が記入する意見書等を参考に給付対象であるか町で審査します。
給付対象となる費用
- 診察
- 薬剤又は治療材料の支給
- 医学的処置、手術及びその他の治療
- 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
- 移送
医療費の助成
- 養育医療の入院に伴う医療費については、他の制度に優先して養育医療給付の対象になります。
- 給付申請が承認されると、指定養育医療機関の窓口で支払う医療費(医療保険自己負担分)を町が公費助成します。ただし、生計を同一とする 世帯員全員の市町村民税額の合計額に応じて計算される自己負担金が生じます。 しかし養育医療は、子ども医療費助助成制度の支給対象となり、実際にお支払いいただく自己負担金は無料となります。
- 対象となるのは未熟児の治療の「健康保険適用分」のみです。健康保険適用外分(おむつ代、差額ベッド代等)は対象になりませんので、窓口で支払っていただく必要があります。
- 受給期間中に市外へ転出した場合には、新しい住所地で新たな申請が必要となります。
対象期間
指定養育医療機関に入院して、未熟児養育医療を開始した日から退院するまで。
(最長で1歳の誕生日の前々日まで)
申請する時期
退院後や病院に医療費を支払った後の申請は、原則として受け付けられませんので、出生届を提出し、子ども医療費助助成制度・健康保険加入の手続きをしたら、早めに申請手続を行なってください。
申請場所
保健福祉課健康推進室(こども家庭センター)
【所在地】鋸南町保田560 保健福祉総合センター すこやか内
【電話番号】0470-55-1002
【開庁時間】月曜日から金曜日(祝日・12月29日から翌年1月3日を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで
申請時に必要なもの
- 健康保険の資格情報を証明する書類 (健康保険証など)
- 母子健康手帳
- 印鑑(シャチハタタイプ不可、自署の場合は不要)
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 身分証明書(運転免許証など)
申請書類
- 養育医療意見書 医療機関で記入してもらいます。書類は窓口で配布します。
- 養育医療給付申請書 申請者(赤ちゃんの保護者)が記入します。書類は窓口で配布します。
- 低体重児出生届 申請者(赤ちゃんの保護者)が記入します。書類は窓口で配布します。
- 世帯調書 申請者(赤ちゃんの保護者)が記入します。養育医療が必要な赤ちゃんと生計をともにしている方全員を記入してください。書類は窓口で配布します。
申請後の流れ
承認されると養育医療券、医療機関宛ての通知をご自宅に郵送します。そちらを医療機関に提出してください。
申請の際に、こども医療費を養育医療の自己負担金に充当させることに同意していただいた方は、納付等の手続を省くことができる場合があります。その際の明細書は、後日保健福祉課から送付します。
継続給付
交付された医療券の有効期限を過ぎてなお当該医療を継続する場合は、事前に当該指定養育医療機関の医師の意見を記した養育医療継続診療協議書を提出していただく必要があります。