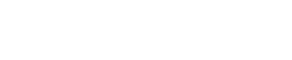本文
町報きょなん2023年4月号・連載
鋸山の日本遺産認定を目指して
鋸山シンポジウムを開催
2月19日に「日本寺から考える鋸山の新たな魅力」と題し、シンポジウムを開催しました。
日本寺の歴史や千五百羅漢に関する講演の後に、道の駅保田小 学校の大塚駅長、千葉大学の安森教授、金谷ストーンコミュニティーの鈴木代表、町資料館の笹生館長の4人によるパネルディスカッションで鋸山や日本寺の新たな活用を話し合いました。
日本寺の知られざる歴史に、来場者は鋸山の魅力を改めて感じていたようでした。
シンポジウムの様子は、YouTubeで視聴できますので、ぜひご覧ください。
鋸山有償ガイド育成講習会修了式
3月4日に鋸山有償ガイド育成講習会修了式が行われ、24人のガイドが誕生しました。
この講習会は、鋸山の魅力を発信する地域人材を育成するため、歴史の勉強から安全管理など全10回の座学と3回以上の現地研修を行いました。
今後はモニターツアーなどでガイド経験を積んでいく予定です。
浮世絵版画摺り体験指導者養成講座
体験プログラム構築事業として、浮世絵版画摺り体験指導者養成講座を開催しました。江戸木版画摺師の松崎啓三郎さんを講師に5回の研修を実施し、8人が技術を学びました。
3月4日には、修了者を講師とした体験会を開催し、15人が歌川広重の「富士三十六景 房州保田ノ海岸」を摺りました。
鋸南病院だより【第22回】院長就任・退任のごあいさつ
山本大夢新院長の就任あいさつ
平素より当院をご利用いただき誠にありがとうございます。
この度、4月1日から医療法人財団きさらぎ会の理事長及び鋸南病院の院長に就任しました。
私の一番の目標は、地域の皆さんに愛され、親しまれる病院を作ることです。そのために患者さんの目線で対話・診察し、よりやさしく、よりわかりやすい説明・診療を心がけていきたいと思います。
また、スタッフもホスピタリティをもって温かい応対ができるような環境整備に努めてまいります。
今後とも、格別のお引き立てを賜れれば幸いです。どうぞよろしくお願いします。
金親正敏院長の退任あいさつ
40年もの長きにわたり、鋸南病院で働かせていただきました。
私は当時千葉保健所長だった大学の同級生から依頼があり、鋸南病院で勤務することになり、官舎に住まわせていただきました。その後、当時横浜で開業していた父の承諾を得て、鋸南病院の院長を引き受けました。
それからは周りの皆さんに支えられながら、何とか院長職を終えることができました。これまでご支援いただいた皆さん、ありがとうございました。
問合せ先 鋸南病院 【電話番号】55-2125
防災の豆知識 第2回 津波てんでんこ
前回の海溝型地震に引き続いてのお話です。
東日本大震災以来、よく言われる言葉で「津波てんでんこ」があります。「津波が来たら各自てんでんばらばらに高台に逃げろ」という意味です。この言葉が普及し、よく「自分だけで逃げれば良いだろう」という方がいますが本当でしょうか?
「津波てんでんこ」の例として「釜石の奇跡」と言われた、鵜住居小と釜石東中の子どもたちの避難は、「各自が一人で逃げた」のではなく、全員で助け合った結果です。当初の避難場所で、後から避難してきた老人に「ここでは危ない、もっと高いところ
に逃げろ」と注意され、子ども同士で小さい子の手を引き、幼稚園児の乳母車を押し、崖では大人たちが非力な子どもを押し上げて、みんなで協力しながら逃げた結果です。注意した老人、手を引く子ども、押し上げた大人、すべての人が協力して奇跡を生
んだのです。もし、協力しなかったら、大半の人は津波に飲み込まれ、「奇跡」が「悲劇」になっていたでしょう。
「津波てんでんこ」の本来の意味・用法は、「『津波てんでんこ』だから自分で逃げられるように準備しよう」、「それぞれが逃げているので無理して探しに行くな」ということです。
実際、「釜石の奇跡」でも、弟とはぐれた少女が、弟を探しに戻ろうとしたところを周囲の大人が止めて避難しました。弟は別の大人に保護され、一緒に避難していたので、姉弟ともに生き延びることができました。
同じく海に面する鋸南町としても、正しい「津波てんでんこ」の精神を持ち、自助の気構えで準備し、地域としての協力を基盤に全員が助かる「強い絆の町」を作っていきましょう。
歴史資料館 連載三七二
市部瀬の惨劇
戦争はいつの時代でも悲劇しか生みません。太平洋戦争末期、日本への本土空襲が高まる昭和二〇年(一九四五)五月八日、安房勝山駅十一時五〇分発の下り列車が、下佐久間の市部瀬の直線の線路にさしかかったところで、アメリカ軍機に空から無差別に銃撃されるという事件が起こりました。
この日、太平洋上から九十九里方面を経てアメリカ軍機P五一約一〇〇機が飛来。千葉、木更津周辺を襲撃した後、三十八機が館山方面に南下したと言います。この内三機が列車を襲いました。
突然バリバリバリという大音響がしたと思うと列車は急停止しました。軍機が波状攻撃を繰り返し、低空で列車に機銃掃射を加えたのです。
乗客らはなすすべなく、死者十三名、負傷者四十六名の犠牲者を出しました。負傷者は勝山病院、武内病院にかつぎ込まれ、医療関係者総出で治療にあたりました。
この日は休日で、久しぶりに故郷へ帰る人たちが多かったことも悲劇でした。川崎の工場に勤務し、三芳の両親に会いに行く途中だった二十歳の男性。試験に合格し、女性ながら念願の鉄道職員となり千葉駅に勤務、初めての休日で館山に帰る途中だった二十歳前の女性。お産のため実家に帰り、生まれたての赤ちゃんを連れて、館山のご主人のもとへ行く途中だった母親。皆銃弾を受けて亡くなりました。その母親は館山の海軍基地から戦地に向かうご主人に面会に行くためでした。幸い赤ちゃんは助かり、地域の方に引き取られ成長したそうです。市部瀬の民家も被弾し、かやぶき屋根が全焼したお宅もありました。
現在の鋸南小学校の校庭にも薬きょう(銃弾を発射した殻)がたくさん落ちていたそうです。
決して忘れてはならない市部瀬の惨劇として、その場所には現在、「恒久平和祈念の碑」が建てられています。
健康通信
あなたの骨は大丈夫? 骨粗しょう症予防を
閉経を迎えた女性や、若いときに極端な食事制限をした人、運動不足、偏食、たばこを吸う、お酒を飲む量が多い、糖尿病や慢性腎臓病の人は骨粗しょう症になるリスクが高いです。高齢の方は、骨折をきっかけに歩けなくなったり、寝たきりになったりします。
昨年の町の骨粗しょう症健診では、受診者の3割が医療機関の受診を勧められました。その内3割が骨粗しょう症と診断され、50代前半や60代前半の方が半数以上でした。
今年度は9月頃に健診を行います。対象は40歳~70歳の女性で5年に一度健診を受けることができます。検診は手首周辺に微量のX線を照射し、時間は5分くらいで負担が少ない検査です。
骨粗しょう症予防のポイント
1.骨の成分であるカルシウムを十分に取る。
牛乳、チーズ、ヨーグルトはカルシウムが豊富で吸収率も優れています。いわしの丸干し、ししゃも、ひじき、切り干し大根、大豆製品などにも多く含まれています。
2.バランス良い食事を心がける。
丈夫な骨を作るためには、たんぱく質やビタミンDも必要です。たんぱく質を多く含む食品には、魚、肉、卵、大豆製品があります。ビタミンDは、きくらげ、干ししいたけ、まぐろ、うなぎ、鮭などに多く含まれています。
3.カルシウムの吸収を阻害しないようにする。
たばこ、アルコール、コーヒー、食塩のとりすぎ、インスタント食品やスナック菓子に含まれるリンの取りすぎは、全身の血流を悪くし、骨粗しょう症のリスクを高めます。これらは、カルシウムの吸収を阻害するので注意しましょう。
4.適度な運動をする。
運動は骨に刺激を与え、新陳代謝を活発にし、骨を丈夫にします。野外での日光を浴びた運動は、ビタミンDの合成を促進し骨の生成に役立ちます。家の中でできる体操なども実行して骨の老化防止や健康づくりに努めましょう。
きょなん学校給食レシピ
沢煮椀
野菜たっぷりの汁ものです。和風の味付けで、野菜の風味とこしょうのアクセントが特徴的な一品です。
材料(4人分)
だし汁・・・・・・・・500ml
しょうゆ・・・・・・小さじ1
塩・・・・・・・・・・・・小さじ1/2
みりん・・・・・・・・小さじ1
こしょう・・・・・・・・少々
もやし・・・・・・・・40g
たけのこ水煮・・40g
にんじん・・・・・・・30g
ほうれん草・・・・20g
しいたけ・・・・・・・1枚
大根・・・・・・・・・・40g
豚肉・・・・・・・・・・30g
ごま油・・・・・・・・小さじ1
作り方
(1) たけのことにんじん、大根は千切り、ほうれん草と豚肉は食べやすい大きさに切る。しいたけは薄切りにし、もやしは水で洗っておく。
(2) 鍋にごま油を熱し、豚肉をよく炒める。
(3) ほうれん草以外の野菜を鍋に入れ、さっと炒めたら、だし汁を注ぐ。
(4) あくを取り、ほうれん草、しょうゆ、塩、みりんを加える。
(5) 器に盛り付け、こしょうをふる。
提供:学校給食センター
わんぱく登場
詩織ちゃん 1歳3か月
鈴木 誠さん・直子さん 第3子 本郷区
お姉ちゃんお兄ちゃんとブロックやボールで遊ぶのが好きなんだ。でも一人にされると泣いちゃうよ。ご飯が大好きで待ちきれなくなるの。保育所でもたくさん食べるんだよ。
お風呂も大好きで声をかけられると、一人でお風呂場まで歩いて行くんだよ。わたし、何でも興味あるの。毎日楽しいこといっぱい!
人の動き
3月1日現在(前月比)
人口 6,974人(+3人)
うち男 3,376人(+4人)
女 3,598人(-1人)
世帯数 3,466世帯(+5世帯)
出生:1人 死亡:9人 転入:22人 転出:11人
誌面で掲載した記事は、中止や内容が変更となる場合がありますのでご了承ください。
※誌面で掲載した記事や写真等の無断転載を禁じます。