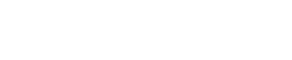本文
町報きょなん2023年3月号・特集(鋸南町名字ランキング)
自分と同じ名字を持つ方がどれくらいいるか気になったことはありませんか。今号では、鋸南町や千葉県、全国の名字ランキングを紹介します。自分の名字について、ご家族や友人と話してみてはいかがでしょうか。
名字の歴史・種類
名字は明治初期まで庶民が名乗ることを許されていませんでした。明治3年の「平民苗字許可令」により誰でも名字(氏)を名乗ることが許され、明治8年の「苗字必称義務令」では、すべての者が名字を名乗ることが義務付けられました。
名字は、同じ氏を名乗る人が全国に増え、氏を区別するために地名などから名乗るようになったことが起源となっています。
氏とは親族や血筋を表しており、地名や職業に由来するものも多くあります。現代では氏・姓・名字の区別はありません。日本では、数え方にもよりますが、30万種類以上の名字があるとも言われています。
| 人数潤 | 鋸南町 | 千葉県 | 全国 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木(292人) | 鈴木(およそ163,000人) | 佐藤(およそ1,842,000人) |
| 2 | 川名(210人) | 高橋(およそ94,800人) | 鈴木(およそ1,778,000人) |
| 3 | 石井(208人) | 佐藤(およそ88,400人) | 高橋(およそ1,392,000人) |
| 4 | 笹生(186人) | 渡辺(およそ76,500人) | 田中(およそ1,320,000人) |
| 5 | 金木(156人) | 伊藤(およそ74,400人) | 伊藤(およそ1,060,000人) |
| 6 | 川崎(135人) ※川崎、川嵜含む |
石井(およそ63,000人) | 渡辺(およそ1,050,000人) |
| 7 | 渡邉(127人) ※渡辺、渡邊ほか含む |
田中(およそ58,500人) | 山本(およそ1,036,000人) |
| 8 | 福原(125人) | 中村(およそ58,500人) | 中村(およそ1,032,000人) |
| 9 | 黒川(105人) | 小林(およそ51,200人) | 小林(およそ1,016,000人) |
| 10 | 池田(102人) | 斎藤(およそ47,800人) | 加藤(およそ878,000人) |
※「鋸南町ランキング」は総務企画課調べ・「千葉県・全国ランキング」名字由来netから引用
名字の由来 トップ5を紹介
第1位 鈴木
発祥は和歌山県と言われ、田の中の穂積みに立てた稲魂招来用の一本の棒を「聖木(すすき)」と呼び、転じて「鈴木」となったとされています。稲魂とは、稲を司る神様です。
第2位 川名
関東を中心に分布しており、千葉県に多いとされています。「館山市川名」や「富津市川名」など地名に由来すると考えられます。安房地域に多い名字です。
第3位 石井
「石の多い土地」として、地形が由来とされています。「井」は井戸の意味もあると言われていますが、添え字の傾向が強いとされています。
第4位 笹生
千葉県南部が発祥とされ、安房の豪族が名乗っていたとされています。全国でも千葉県が最多と言われており、鋸南町、富津市に多い名字です。
第5位 金木
金や鉄にまつわる地域が由来とされています。全国でも千葉県が最多と言われ、鋸南町でも江戸時代から名乗られていたと言われています。
鋸南町に残る頼朝からもらった姓
石橋山で敗れ、海路安房国に逃れ竜島に上陸した源頼朝は、竜島の人々の親切なもてなしに感激し、姓を与えることにしました。
ひれのりっぱな魚を献上した者に「鰭崎」。貝を献上した者に「生貝」。家に松が茂っていた者に「松山」。しばの葉で茶を入れてくれた者に「柴本」。菊が飾ってあった家の者に「菊間」。他に理由はわかりませんが、「久保田」、「中山」があり、これらを竜島の七姓と呼んでいます。
頼朝を乗せて来た船の船頭で、この地が気に入り定着した者らは、船用語から「艫居」、「間」、「渡」となったそうです。
また、石橋山に参戦し、この地に移り住み帰農した者が、市井原の「早川」だと言われています。
「矢生」は梶原氏の流れで弓の名手だったからとか。頼朝が通る道の草を刈ったから「刈込」、江月を頼朝が通ったとき、名馬を献上した者に「馬賀」など、頼朝からもらった姓と伝わります。「馬賀」は江月の鶴ケ峰神社の神主だったそうです。
頼朝が上陸後落ち着いた竜島神明社の神主だったのが「左右加」氏。頼朝に左右から兵が多く加わってくれるように祈願してくれたお礼にいただいた姓とも言われます。
別の話も伝わります。頼朝が村人らに、これまでのお礼に安房一国を与えようと言います。ところが彼らは「安房一国」を「粟一石」と勘違い。「頼朝様、それより姓をください」と言います。頼朝は欲のなさを笑い「そうか、ばかだなあ」と独り言。それを姓をくれたものとまた勘違いし、「左右加」「馬賀」を名乗るようになったと言います。