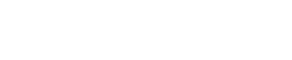本文
町報きょなん2022年2月号・特集(2)首都圏大学連携 「鋸南プロジェクト」の活動紹介
首都圏大学連携「鋸南プロジェクト」の活動紹介
工学院大学、早稲田大学、日本女子大学が参画する「鋸南プロジェクト」は、町と協働して地域活性化を目指す「域学連携」に取り組んでいます。
平成25年度都市交流施設整備事業での保田小学校のリノベーションを機に始まった鋸南プロジェクトの活動は今年で8年目を迎えました。
このプロジェクトは、平成29年度の旧鋸南幼稚園・旧佐久間小学校等の公共施設の再生プラン検討への協力を経て、平成30年度から町の受託研究である「域学連携」として町と学生チームが密接につながり、継続的に活動していく体制となりました。
今年度は昨年度のテーマ「二拠点居住」をより発展させていくため、新たに「新モビリティによる交通整備」「農地活用提案」を加えて、研究を進めています。
二拠点居住
「二拠点居住」とは都市部と地方部に二つの生活拠点を持つ暮らし方を言います。
昨年度は実際に町へ移住してきた方や二拠点居住をしている方へのヒアリング調査を行い、情報発信力の弱さや、お話を聞いた方全員が新築ではなく空き家のリフォームによって住む場所を確保していたことがわかりました。
その結果を受け、私たちは、毎月定額料金で全国どこでも住み放題のサブスクリプションシステムへの参加によって情報発信していくことに着目しました。
●サブスクリプションシステムとは?
例)「ADDress」が提供するサービス
日本各地で運営する家に定額で住み込めます。長期滞在もでき、何度でも住居を移動できます。
忙しい暮らしの中でも生活の質を高めたい方や、自然豊かな環境でリモートワーク・テレワークを行いたい方など、幅広い世代・目的で利用できます。
二拠点居住促進のための調査
私たちは二拠点居住の促進のため、次の3つの調査を行いました。
(1)拠点となる空き家の調査
勝山港通り商店街周辺で二拠点居住の拠点となる空き家の現状を調査し、平成27年度と現在での空き家情報の更新を行い、私たちの目線から魅力などを調査しました。
町での日常風景は私たち都市部に住む者から見ると、とても魅力的です。しかし、「住む」という視点を置いたとき、やはり暮らしの利便性が重要になってきます。
そのために「新モビリティによる交通整備」「農地の活用」について研究を進めています。
(2)趣味・仕事となる農地の活用の調査
町の温暖な気候を活かし、二拠点居住者の趣味や仕事として農地の活用が有効であると考えます。実際に町では空き農地が多くあり、現地調査では、再生・利活用が可能な農地である「遊休農地」がどれくらいあるのかを調査しました。
その結果、遊休農地は江月地区の「水仙ロード」の周辺に多く分布していることがわかりました。
(3)二拠点居住者・地域の人の足として「新モビリティ」導入のための調査
新モビリティとは、電気で動く新しい乗り物で、小型な物が多くあります。町に住む高齢者の方や二拠点居住者の方が気軽に移動するのに最適な乗り物です。
これらの乗り物を置くことが可能かを主にバス停を中心に調査しました。その結果、バス停に置くことは可能ですが、通行するための道路の整備が必要であるということがわかりました。
以上の調査結果をもとに、私たちは実際に新モビリティによってどの道路をつなぐ必要があるのか、遊休農地の今後の活用、新モビリティへの関心等のアンケートを交えて調査を進め、次年度に活きる研究を行っていきます。今年度の取り組みは次号でも紹介します。
(文責 工学院大学大学院修士1年 鋸南プロジェクト学生代表 若杉玲来)