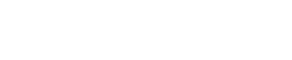本文
国民健康保険料の料率と計算方法
1年間の国民健康保険料の計算方法
次の項目を基に算定し、1年間の保険料額が決まります。
| 所得割 | 世帯の所得に応じて計算 |
|---|---|
| 年間保険料額 = 医療保険分 + 後期高齢者支援金分 + 介護保険分 | |
| 均等割 | 世帯の加入者数に応じて計算 |
| 年間保険料額 = 医療保険分 + 後期高齢者支援金分 + 介護保険分 | |
| 平等割 | 1世帯にいくらと計算 |
| 年間保険料額 = 医療保険分 |
※介護保険分は、40歳以上65歳未満の方のみ適用されます。
※上限額(賦課限度額)は、医療保険分66万円、後期高齢者支援金分26万円、介護保険分17万円です。
※所得割額の算出方法は、(令和6年中の総所得金額など-基礎控除43万円)×税率です。
※合計所得金額が2,400万円を超える場合は基礎控除額が減少し、2,500万円を超える場合は基礎控除の適用がありません。
※国民保険料では、住民税や所得税のような扶養控除などの各種所得控除の適用はありません。
令和7年度の保険料率
●保険料率の改正
医療の高度化や被保険者数の減少などにより、国民健康保険の財政状況は厳しく、料率を改正せずに据え置いた場合、数年のうちに国保財政調整基金(貯金)はなくなり、国保会計が赤字となることが見込まれました。
このため、令和7年度の料率を次のとおり改正します。加入者の皆さんにはご負担をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いします。
| 区分 | 医療保険分 | 後期高齢者支援分 | 介護保険分 | |||
| 改正前 | 改正後 | 改正前 | 改正後 | 改正前 | 改正後 | |
| 所得割 | 6.30% | 6.72% | 2.40% | 2.33% | 2.35% | 1.90% |
| 均等割 | 29,000円 | 31,300円 | 15,500円 | 16,000円 | 15,000円 | 16,000円 |
| 平等割 | 18,000円 | 19,600円 | - | - | - | - |
| 限度額 | 650,000円 | 660,000円 | 240,000円 | 260,000円 | 170,000円 | 170,000円 |
※令和7年度の保険料額については、7月中に送付される納入通知書でご確認ください。
保険料軽減額
所得に応じた保険料の軽減
| 医療保険分 | 後期高齢者支援金分 | 介護保険分 | ||
|---|---|---|---|---|
| 均等割 | 平等割 | 均等割 | 均等割 | |
| 7割軽減額 | 21,910円 | 13,720円 | 11,200円 | 11,200円 |
| 5割軽減額 | 15,650円 | 9,800円 | 8,000円 | 8,000円 |
| 2割軽減額 | 6,260円 | 3,920円 | 3,200円 | 3,200円 |
7割軽減額
被保険者(擬制世帯主を含む)の合計所得金額が43万円以下の世帯+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
5割軽減額
被保険者(擬制世帯主を含む)の合計所得金額が43万円+(被保険者数×305,000円)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
2割軽減額
被保険者(擬制世帯主を含む)の合計所得金額が43万円+(被保険者数×560,000円)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
未就学児に対する均等割保険料の軽減
未就学児の均等割保険料は、半額になります。所得に応じた軽減を受けている世帯の未就学児については、軽減後の保険料が更に半額になります。
後期高齢者医療制度への移行による減額措置があります
75歳以上の方が国民健康保険や被用者保険から後期高齢者医療制度へ移行した場合、同一世帯の国保加入者には次のような減額措置があります。
75歳以上の方が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行し、74歳以下の方が引き続き国民健康保険に加入の場合
- 保険料の軽減を受けている世帯は、世帯構成や収入が変わらなければ、5年間今までと同じ軽減を受けることができます。
- 国民健康保険の被保険者が1人となる場合には、5年間医療分の平等割額が半額になります。
75歳以上の方が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行し、その被扶養者(65〜74歳)が国民健康保険に加入する場合
新たに国民健康保険に加入し、保険料を納めることになった方は、2年間、医療分の均等割額が半額に、さらに被保険者が1人の場合などには、平等割額も半額になります。